「震災後、トマトの栽培を始めることになりビニールハウスを建てました。その時、子供たちが楽しそうに走り回っている光景を見て『妖精』のように見えたんです。」
宮城県名取市にある美食農園Lafata(ラ・ファータ)。
半澤さんは、名取の希望を育むこの場所に、イタリア語で〝妖精〟を意味する「ラ・ファータ」から名前をつけました。
仙台空港から飛び立つ飛行機の轟音にびくともしないビニールハウスは、海に面した田園風景の中で悠然と佇んでいます。ハウスの中では、真夏の蒸し暑い空気にも負けず青々としたトマトの幹や葉が美しく背を伸ばし整然と並んでいます。その生命力と迫力に圧倒されずにはいられません。


当初はトマトの栽培に関するノウハウがなかったため、トマト栽培の修行にも赴いたそうです。トマトは消費量が安定しており、作り方や品質による差別化がしやすい野菜の一つでした。そして、土地に合わせた研究を進めるうちに、半澤さんのトマトは味わい深く、濃厚なトマト本来の美味しさのある実を実らせるようになったのです。
今や、新鮮なトマトが直売所に並ぶとすぐに売り切れてしまうほど評判を呼んでいます。そのため市場への卸しはほとんど行わず、直売所での販売と飲食店との直接取引に力を入れています。
半澤さんは「農業の大規模化と中小規模農家の二極化の中で、我々はとにかく味にこだわっていかなければならないと考えています。大規模な方は、とにかく量を作らなければならない。我々は、こだわり続けること。いいものを作っていれば、きっと買ってくれる。最近の市販のトマトは味があまり感じられないという声を聞いています。でも、ラファータのトマトはしっかりトマトの味がするって。だからここのしか食べられないんだって言う方がたくさんいます。だから味にこだわり続けたい。」と語ってくれました。
大切に育てられた貴重なトマトをナチュリノで使用させていただいていることを実感し、改めて心から感謝しております。

ラ・ファータは、「農家」として生きる姿勢と「経営」とのバランスを模索しながら半澤さん自身が実践している場所です。気候変動の影響で、暑さの厳しい夏のトマトの収穫は難しくなっています。
「近年は夏のトマトというものに限界を感じてきているので、トマトに代わるものとして白いとうもろこしを作ってみました。来年もうちょっと増やせたらいいですね。」
『伊達真珠』という名のその貴重な白いとうもろこしを、今年の夏は特別にナチュリノ店頭での販売と、ジェラートにして週末限定で販売させていただきました。
半澤さんが名取の地で自分たちの農業の基盤を築く最中、国内では、ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、農業の効率化や品質向上を図る新たな動きが活発になっています。
「やれるもんならやってみたいけど、そのためにまず大規模化が必要なのかなと思う。中央でそういう動きがあっても小規模経営の農家には伝わってこない。我々は小規模農家の中でも若い労力を持っている人たちがいて、今までは各々でやっていたけどそれをまとめていく人がいてもいいのかなと思う。」と、地域内での連携の重要性を強調しています。


「美味しいものを食べたいというのは、一つの人間の基本的な欲求じゃないですか。美味しいものを食べたいという欲がないと、人間じゃなくなっちゃうような気もします。やっぱり、美味しいものを作りたいと私は思います。もちろん、経営として成り立つことは重要ですが、ただ簡単に作れる品種であるとか、赤くて丸ければなんでもいいという考えにはならないですね。
私たちは、ずっと直売をしていてお客様の顔を見ています。お客様が美味しいと言ってくださることは何よりの励みです。ここのトマト以外は考えられない、その一言に尽きます。
人々を幸せにするために美味しいものを提供できる、それが最も幸福なことだと思います。これがなければ、明日もこのハウスに来る気にはなれません。作業は大変ですから。その言葉がないと、どれだけ利益を上げていようと、私はその場所に足を運ぶ気にならないでしょうね。」
半澤さんにとって、お客様の顔が見えることや、近くにいる人々の食べ物の豊かさを守り抜くことが、何よりも力強い原動力となっています。
「まだまだ足場を固めていきます。とにかく名取・宮城にしっかりとした根っこを張りたい。東京から買いたいという要望も届いているのですが、まずは宮城や東北の人々に味わっていただき、広がっていければと考えています。微力ながら、まずは我々の近くにいる人たちの食の幸福を満たしたい。名取・宮城にいるからラファータのトマトを食べれるんだということを大切にしたい。」
勇気を持った挑戦とその誠実さ、真摯な姿勢が、これからもラファータの畑から宮城・名取の食の幸福に、根を張っていきます。



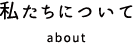
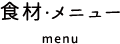
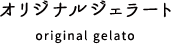




![[インタビュー]人々を幸せにする美味しいものを。味わい深く濃厚なこだわりのトマト](../img/02_interview6_main.jpg)
![[インタビュー]人々を幸せにする美味しいものを。味わい深く濃厚なこだわりのトマト](../img/02_interview6_sp_main.jpg)



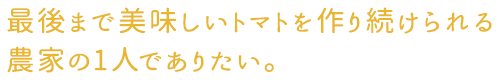

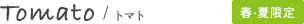
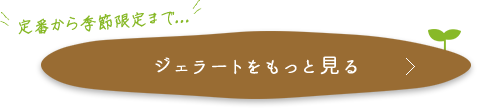

![[インタビュー] Rice(お米) 美田園ファーム/大友さん](../img/00_pickup_img01.jpg)
![[インタビュー] Milk(牧場ミルク) 小松牧場/小松さん](../img/00_pickup_img02.jpg)
![[インタビュー] Tomato(トマト) 美食農園ラ・ファータ/半澤さん](../img/00_pickup_img06.jpg)

 Google Mapsで開く
Google Mapsで開く